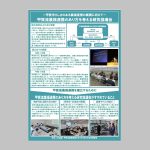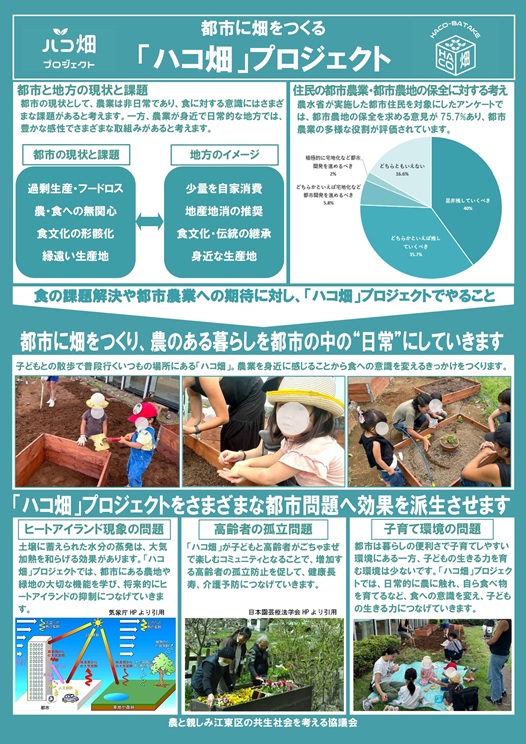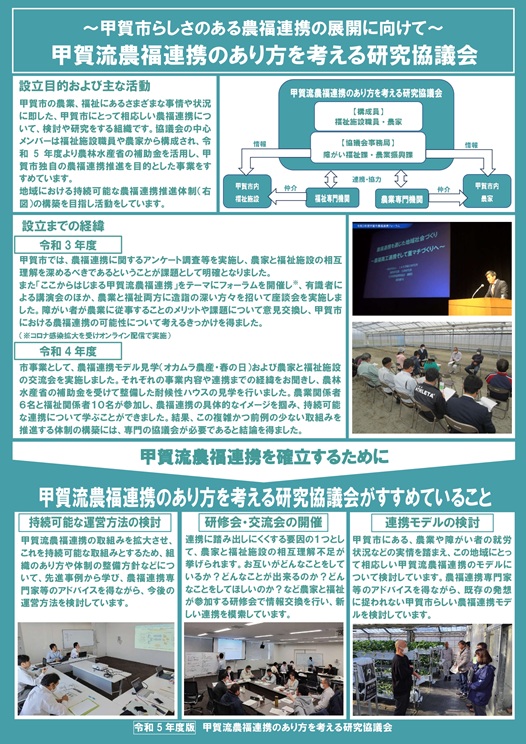広がるHUB’sの活動
私たちは、4つの活動方針のもと、様々な取り組みを生み出してきました。
ここでは、その一例をご紹介します。
六次産業化/耕作放棄地(中山間)
都市農業(都心)/農のある暮らし
栗東529(こんにゃく)プロジェクトPRパネル
ハコ畑プロジェクトPRパネル
ハコ畑プロジェクトPRパネル
空き家/地域再生(中山間)
地域協議会/独創的農福連携
甲賀流農福連携プロジェクトPRパネル
甲賀流農福連携プロジェクトPRパネル
都市農業(地方都市)/農のある暮らし
地域資源/地域再生(中山間)