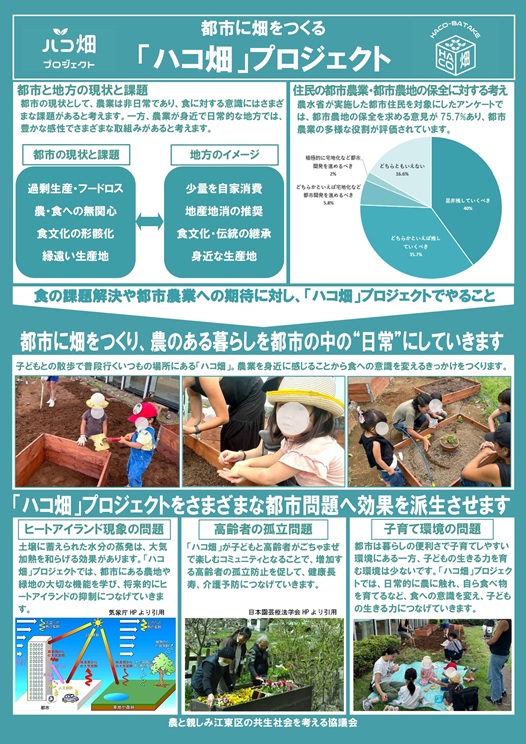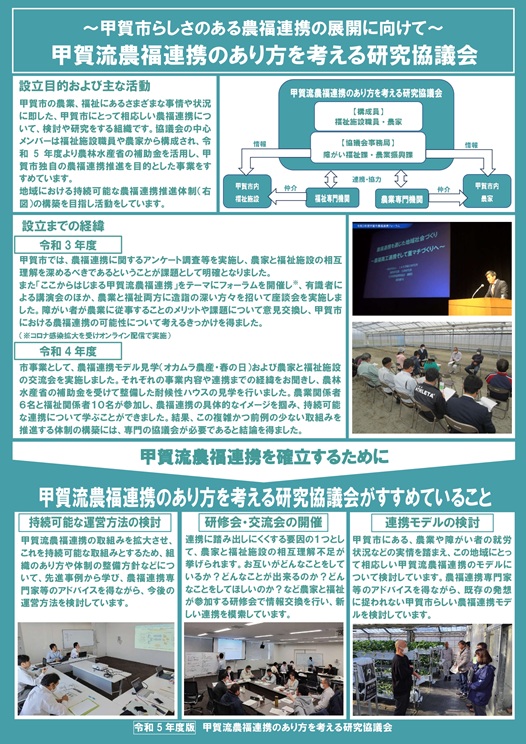はじまりと気づき
HUB’sの原点は、農業(農)と福祉(福)をつなぐ「農福連携」です。障がいのある方の就労機会を生み出し、農家の現場とつながりながら、役割を持って働ける場を増やしてきました。活動を重ねるうちに見えてきたのは、担い手不足という表層だけでなく、子どもたちが農に触れる機会の減少や、「農業はしんどい・もうからない」という印象が世代を越えて受け継がれているという、より深い社会の課題でした。
だからこそ私たちは、
—農を“体験”として取り戻すこと—
—楽しさも大変さも含めて身体で知ること—
そして福祉を“特定の人の支援”に限定せず、
—地域に生きるすべての人の暮らしと役割へと広げて捉えること—
に軸足を置いてきました。貸し農園や体験農園、マルシェを通じて親子や地域が交わり、都市と農村が往来する。そこから「働くこと」の意味も、お金のためだけでなく生きがいと幸せのためへとつながると信じています。

活動の根幹にある、2つの気づき
【二つの気づき】私たちが直面した、見過ごされがちな社会課題
私たちが大切にしてきた気づきは二つ。
人と人、人と社会を結び、新たな可能性をひらくこと。
そのつながりから新しい価値が生まれ、地域や社会を豊かにすること。
この学びをもとに、長年の実践を通して二つの根本課題に向き合う必要があると確信しました。

1)働くことの価値観の崩壊
何が起きているか:働くことが「お金のため」という手段に片寄り、貢献や役割から得られる本質的な喜びが見えにくくなっています。
なぜ問題か:報酬だけを軸にすると多幸感が得にくく、低賃金や単調さを理由に「不幸せ」が増幅。役割の実感や感謝される体験が失われ、働くこと自体が負担になります。
私たちの考え:役割・必要とされる実感・「ありがとう」が生きがいを生み、その結果として経済がついてくる。働くことを生きがいと幸せのために再定義することが必要です。
2)地域社会の断絶
何が起きているか:子どもたちが農に触れる機会を失い、親世代の「農業はしんどい・もうからない」というイメージが継承。地域への愛着が薄れ、担い手不足が深刻化しています。
なぜ問題か:人と人、人と自然の距離が広がると、地域の誇りや共助が弱まり、人口流出・産業衰退・景観や文化の喪失へと連鎖します。
私たちの考え:幼い頃からの本物の体験(楽しい/大変の両面)と、都市と農村の交流がカギです。身土不二(しんどふじ)=「人間の身体と土地の恵みは切り離せない」の感覚を取り戻し、地域を“自分ごと化”する土壌をつくります。
HUB’sの活動を支える3つの信念
気づきから得た方向を日々の実践に落とし込むために、HUB’sは3つの信念を掲げます。
これは、活動の判断基準であり、関わるすべての人に共有したい合言葉です。
1)「はたらく幸せ」を創り、役割と誇りへとひらく
役割や誇りを持ってはたらくことを、生きがいに変えていく
私たちは、誰もが自分の役割に自信と誇りを持ち、生き生きと働ける社会を目指しています。
障がい者支援や農福連携の活動は、単なる労働力の提供ではありません。
働くことで得られる「ありがとう」の言葉や成長の喜び、地域の一員としての役割を通して、すべての人が生きがいを実感できる環境をつくります。

2)「地域」を、誰もが暮らしやすい場へと耕す
親子や世代、都市と農村を結び、愛着ある地域を育てる
私たちは、地域に根ざした活動を通じて、親子、地域住民、都市と農村をつなぎます。
HUB’sの多様な活動は、世代間の交流や地域コミュニティの活性化を促し、誰もが安心して暮らせる温かい地域づくりに貢献します。
地域の農産物や風景に触れる体験を通して、地域への愛着や誇りを育み、次世代につなげることも私たちの重要な使命です。

3)「社会」の課題を、次世代に持続可能な価値としてつなぐ
企業や行政、市民を結ぶハブとして、持続可能な価値を創出する
私たちは、特定の分野に留まらず、地域、行政、企業、人々をつなぐハブとして機能します。
孤立しがちな「点」と「点」を結び、地域の社会資源や人々の「やってみたい」という意欲を、新たな価値へと転換します。
社会の課題を自分ごととして捉え、解決に向けて行動する人を育てることで、持続可能な地域社会を次世代へとつなぐことを目指します。

HUB’sの4つの活動
3つの信念を現場で形にする具体の器が、HUB’sの「4つの活動」です。
二つの気づきをエンジンに、信念を羅針盤にして、日々のプロジェクトを動かしていきます。
1)はたらく幸せを創る活動
役割を実感できる仕事の場と、成長が見える学びの機会をつくります
私たちは、働くことを通して、一人ひとりが持つ可能性を信じ、それを単なる義務ではなく、自己実現のための喜びへと変えていくことを目指しています。既存の枠組みにとらわれず、人々の多様な才能や特性が最大限に活かされる場を創造します。このプロセスを通じて、誰もが役割に自信と誇りを持ち、自らの人生を豊かにできる社会を築いていくこと。働くことの真の価値を再定義し、それを社会全体に広めることが、私たちの使命です。

2)地域と未来をはぐくむ活動
親子・世代・都市と農村を結び、地域の愛着と誇りを次世代へつなぎます
私たちは、地域に開かれた活動を通して、単なる「住む場所」としてではなく、人々が「ともに未来を創造していく場所」へと変えていくことを目指しています。農を通じた交流を起点に、世代や立場を超えた人々の温かい繋がりを育むことで、次世代が「住み続けたい」と心から思える魅力的なコミュニティを形成します。農地の保全や景観の維持といった活動は、私たちが守るべき地域の財産であり、それらを次世代に誇りをもって引き継ぐこと。それこそが、私たちのビジョンです。
-300x200.jpg)
3)社会の価値を引き出す活動
見過ごされがちな課題に光を当て、新しい価値を創造します。
私たちは、見過ごされがちな資源を活かし、社会に存在する様々な課題や矛盾に対し、新しい視点と創造力で解決策を生み出す挑戦をしています。人々の声に耳を傾け、そこに隠れた本質的な価値を見出す。そしてそれを革新的なアイデアと結びつけることで、社会全体に新しい可能性を示します。「福祉」には、障がい者、子ども、高齢者といった特定の対象だけでなく、地域に生きるすべての人々の暮らしが含まれています。私たちは、当たり前だと思われていた社会の枠組みを超え、未来へと続く持続可能な価値を創造します。

4)社会の「ハブ」となる活動
行政・企業・市民をネットワークし、出会いと協働を加速させます
私たちは、社会に点在する様々な要素を、有機的に結びつける役割を担います。孤立しがちな「点」と「点」をつなぎ、全体としての「面」を豊かにすることを目指し、地域住民、企業、行政、そして様々なNPOといった多様な主体を巻き込みます。それぞれの強みを掛け合わせることで、一人では成し得ない大きな社会貢献へと発展させていくこと。都市と農村、異なる価値観を持つ人々を繋ぐことで、新しい共生社会のモデルを創造し、社会全体に活力をもたらすこと。それこそが私たちの「ハブ」としての役割です。
-scaled-e1755674745639-300x169.jpg)